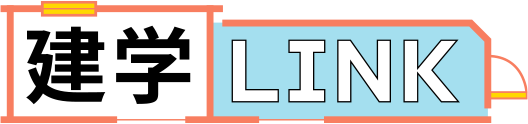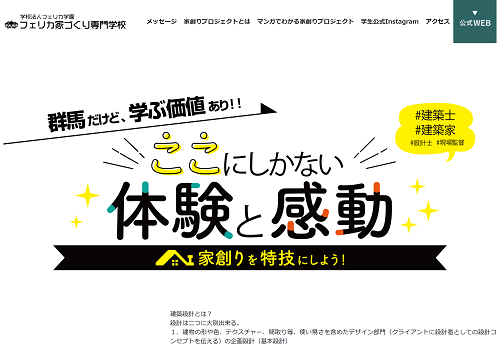建築士は換気の知識も知っておこう
建築士なら、換気のメカニズムを理解しておきましょう。換気は建物の機能性を考える上で重要であり、利用者の健康にも影響を与えるからです。スムーズな換気環境があれば、1年を通して穏やかに生活できます。建物と換気の関係について解説します。
換気が必要な理由
換気をしたほうがいいのは、明確な理由があるからです。その理由について解説します。
湿度や結露予防のためにも大事
換気をしないと、湿気が停滞して生活環境が悪くなります。窓を開いて換気をするだけで、建物内の湿気を外へ出せるのです。梅雨のように雨がたくさん降る時期に限らず、建物内に湿気はあります。炊事場、風呂場、部屋干しの洗濯物にも湿気はあるのです。
湿気が停滞し続けると、結露も起きます。特に気密性の高いマンションの方は、室内の温度は安定していますが、その分、外との気温差が大きくなりがちです。湿気がこもれば、窓や壁や天井に結露が発生しやすくなります。結露は、快適性に限らず建物の寿命や強度にも悪影響を与える厄介なものなので注意が必要です。
健康を考える上でも換気は大事
換気は、健康を考える上でも無視できません。換気をしないと、室内に二酸化炭素が充満することになります。換気をすれば充満した二酸化炭素を逃し、酸素を取り入れることができるのです。汚れた空気を出し、キレイな空気を取り入れるというだけでも、気持ちよくなります。気分転換や心のリフレッシュに役立ちます。
湿気が停滞すると、カビやダニが発生しやすい環境になるでしょう。シックハウス症候群のリスクも高まります。気持ちの問題で終わらず、具体的な健康被害が生じる問題ばかりです。また、冬場にストーブを利用している方は、換気を行わないと酸素濃度低下による一酸化炭素中毒のリスクも高まります。健康な生活を送るためにも、換気は重要です。
換気をしないとどうなるのか
換気なんてしないと、結露や、カビやダニといったハウスダスト、一酸化中毒のリスクまで高まりますが、放置すると具体的にどうなるのでしょうか?その点を解説します。
結露で木の柱が腐り強度が一気に低下
結露はカビやダニが繁殖する原因になります。同時に柱を腐らせるきっかけになるのです。壁の中の柱や土台が腐ると、表面的にはわからないかもしれませんが、ちょっとしたきっかけで倒壊しかねません。大きな地震があれば致命的です。家という重要な財産が失われるだけではなく、倒壊すれば家族全員の命をおびやかすリスクがあります。
ダニやカビやハウスダストによる危険なアレルギー
換気をしないとカビやダニが発生しやすくなり、汚れた空気が停滞することになります。結果、ハウスダストとして、健康を蝕んでいくのです。ハウスダストは室内にある塵全般当てはまります。ハウスダストによるアレルギーとして、鼻炎や気管支喘息やアトピーなどの症状が引き起こされるのです。
一酸化炭素中毒は命もおびやかされるほど危険
非常に危険なのが一酸化中毒でしょう。冬場、ガスや石油ストーブを利用しているご家庭の場合、換気をしないと生命の危険にもつながります。
一酸化炭素は無味無臭ですが毒性が強い気体です。空気中の濃度が0.02%になると、頭痛、吐き気、めまいが生じ、最終的に生命をおびやかされるほどの危険性があります。ガスや石油ストーブは、室内の酸素で燃焼する仕組みです。
換気をしないと空気が汚れ、酸素濃度が低下することで不完全燃焼が起き、一酸化炭素が増えて、中毒症状につながります。換気は軽く考えがちですが、油断すると、生命の危険もある大問題です。
換気時の空気量についても定められている
換気をするときに必要な空気量を、必要換気量といいます。機械換気設備の換気能力は、必要有効換気量より高くなければならないと建築基準法で定められています。たとえば、床面積50m2、天井の高さが2.5mだと、必要有効換気量は0.5(1時間の換気回数)×50m2×2.5=62.5m3/hです。
換気の種類
換気には大きく分けて、自然換気と機械換気の2種類があります。それぞれの特徴と違いについて解説します。
自然換気
自然換気は、風や室内と外の温度差で換気をする方法です。窓を開ける行為も自然換気に当てはまります。温度差による自然換気は、冷えた空気が暖かい場所に流れる仕組みを利用した換気方法です。冷房が効いた部屋の窓を開けると冷気は外へ出ていき、暖房で暖かい状態で窓を開けると、冷たい空気が入って来ます。
また、冷たい空気は下へ流れ、暖かい空気は天井へ上がるのが特徴です。その性質を利用し、冷気対策は床に近い場所に窓を設置し、暖かい空気を流すため、天井の近くに換気窓を設置している建物もあります。
機械換気
機械換気は、機器の動力を使った換気で、第1種、第2種、第3種があります。それぞれに適した部屋はありますが、機器という強力な動力を使用するため、自然換気よりも換気する力は大きいです。なじみのある機械換気として、換気扇があります。
機械換気の種類
機械換気の1種、2種、3種の違いを解説します。
第1種換気
第1種換気は、ファンにより給気と排気の両方を行います。吸気量、換気量の両方の量を確実に確保したい場合に適した方法です。ファンにより、室内にある圧力を周囲よりも高くする、低くするというふうに調整できます。
バランスを考える方にとって選択肢に入るでしょう。バランスがいいということは、どんな部屋でも柔軟に対応できるともいえます。特別、吸気量を増やしたい、排気量を増やしたいというケースでなければ、オールマイティに活躍する換気方法です。
第2種換気
給気ファンと排気口を設置する換気方法です。室内に給気するときはファンを使います。室内にあった空気は排気口から外へ出ていくのが特徴です。ただ、気密性が低いと壁へ湿気が入り込み結露のリスクがあります。
給気ファン付近の外壁から空気が排気される、遠い場所だと期待通りに換気できないリスクもある方法です。そのため、建物は気密性の高さが求められます。手術室やボイラ室などに向いているタイプです。給気力を特に高くしたい方に向いています。
第3種換気
排気をファンで行い、給気は自然換気の給気口で行う換気方法です。積極的に排気することで、室内の空気圧が低くなります。ただ、外より、室内気圧が低くなると、床下や天井裏、壁の中にある空気が室内に出て来る問題には注意が必要です。第3種換気をするなら、居室間に気密層、通気止め、建材、天井裏の換気など対策が必要でしょう。
感染症室やゴミ処理場、トイレ、キッチンなどが適しています。臭いや熱、汚染された空気が発生する箇所に排気ファンを設置すれば、周辺への拡散予防につながるのです。
換気設備の種類
換気設備も複数種類あります。各設備に特徴や強みがあるため、押さえておきたい知識です。
プロペラファン
一般的に家庭内で使われている換気扇のことです。大きいほど風量は増加するのですが、静圧は低いという特徴を持っています。そのため、ダクト接続には向いていないでしょう。外壁に直接設置できるといった、施工の手軽さは魅力です。
高静圧プロペラファン
高静圧プロペラファンのメリットは、強力なモーターを使った一般家庭用のプロペラファンよりも高い静圧です。高静圧だからこそ、大空間の換気にも適しています。静圧が高いことで、ダクト接続ができる点は大きなメリットでしょう。
シロッコファン(多翼送風機)
シロッコファンは、多翼送風機とも呼ばれ、ダクト接続用や台所レンジのファンなど、幅広い用途で採用されているタイプです。水車と同じ原理で動作し、羽根車の部分には、幅の狭い羽が多数あります。風量のコントロールや高い静圧が魅力です。
ターボファン
形はシロッコファンのように羽つきですが、幅が狭いタイプではなく、広くて後ろ向きの羽が異なる点です。他のファンと比較しても、静圧の高さが魅力です。その高い静圧能力から、小さいものならパソコンのファン、大きいものなら工業用でも採用されています。